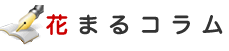長いこだわりでした。思春期の生徒たちには、好き嫌いなんてたいていは、いつか自分で決めつけただけだ、大切なのは意識改革なのだと偉そうに言っているくせに、こびりついたような違和感が、ずっとありました。
ひとつには、幼い頃に回りの大人たちが、露骨に差別的な言葉を言っているのを聞かされ、すりこまれてしまっていたということがあるかもしれません。それでも、青年期には、より志高からんと自己改革に励むものですし、私もそうあろうとしていました。しかし例えば、男同士の雑談の中で、もうすぐ結婚する友人の相手だけど、どんな人なんだという話になったときに、誰かが「日本人じゃなかったりして」と軽口をたたく。すぐに「どうするよ、式場に行ったら向こうの親戚が、チマチョゴリでズラーっと並んでたら」と応えると、ひと笑い。
今でも覚えているのですから、私なりにひっかかるものがあったのでしょう。当時は、いやこれは差別ではなく、意外性が面白いんだと思い込もうとしていたのですが、一方で、もし我が身に本当に起こったら、親戚にいろいろ言われるかもなと、逃げ腰になる自分がいました。表面上は大らかさを装った裏で、自分だけが知っていた偽善性。
テレビなどで文化人と称される人が、そういうこだわりとは無縁のように、韓国の文化や友人を紹介していたりすると、うさんくさいなあ、俺はそんな気持ちには本心ではなれないけどなあと、半分自己嫌悪も含んで感じていました。
そんなある種のこだわりが、今回の旅でものの見事に解消されたのです。必要なのは「行ってみる」という行動と、ふれあう実体験だったのです。そして行く先々で熱すぎるほどに歓迎されました。3日間ついてくれた、日本では新宿御苑が好きだったという通訳の青年などは、最終日に空港が近付いただけで「悲しくなってきました」と半泣きの顔で惜しんでくれたくらいです。皆、誠実でまごころのこもったもてなしでした。
あれは確か1997年。フランスワールドカップ予選で、先に本選出場を決めた韓国の地に乗り込んだ、後の無い日本チームに、大きな横断幕のメッセージが掲げられました。
「Let’s go to the France together」思うに、二国の関係は、あのとき一陣の爽やかな風が吹き抜け、転機になったように思います。その後の「韓流ブーム・韓流人気」では、いちはやく女性たちが韓国の魅力に気づき、配慮や義務ではなく、「あこがれ」を持っておつきあいする時代が来ました。
宴の最中には、九州の田舎町のさらに数十年前にタイムスリップしたような感覚がありました。同じ儒教を土台にした兄弟国として、仲良くやっていきたい。飛行機の中では、差別って「コンプレックス」の裏返しだし、相手の生活や感性を知らない「無知」がつくる「こころの硬さ」みたいなものだなと考えました。子どもたちには、いろいろな文化と触れ合い、より多くの人と交わる経験をさせたいものです。
花まる学習会代表 高濱正伸