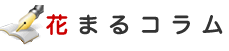『いのちのバトン』2013年8,9月
今年、一冊の文庫本の解説を頼まれました。朱川湊人さんの「オルゴォル」という本です。離婚した母と古い団地に住む5年生の少年ハヤトが主人公。いじめや学級崩壊や給食費未納など現代的エピソードのただ中にあるごく普通の少年が、ひょんなことから鹿児島までの一人旅に出て、様々な心揺さぶる出来事や「外の師匠」と出会い、たくましい青年へと脱皮していく物語です。私は、その解説の最後を、こう締めくくりました。
――本当に偶然なのだが、「高濱先生と行く修学旅行」という名のサマースクールで、知覧の特攻平和祈念会館に行ったばかりであったし、翌年には原爆記念館に連れていくことを予定していた。「忘れてはいけない。子どもたちに伝えたい」という思いは、著者と共有しているだろうし、この小説自体が、私にとっての半袖の青年のような導きをしてくれているようにも感じる。孤独死していく人にも、きっとそれぞれの人生や輝いた日々があったであろうと想像することや、戦争の頃に将来の子孫たちの平和を心から願った人たちがいたことへの想像力には欠けていたからだ。たまたまの依頼、無い時間をやりくりしての読破と解説執筆であったが、手を止めてじっと考えることも多かった。この一冊に巡り合えて幸せだったと思う。我が子についての心配が、泉のようにあふれるお母さんたちが、これを読んで「よし、旅に出そう」と変わってくれると嬉しい。――
今年の「修学旅行」は、長崎がメインでした。一回目が水俣、二回目は知覧、そして今回の長崎。私が目指してきたのは、まさに小説中でハヤトがそうであったように、親のいない旅に出て、人間の引き起こした悲しい現実に触れ、魂を揺さぶられ考え抜いてもらうきっかけを与えられればということでした。特に今回は、人前で意見を発表するプレゼンやディベートの力をつける端緒にできればとも考えていました。その試みは概ね成功し、初日は小学校の学級内でよくある、独特の型にはまったリズムでしか発表できなかった子たちも、最終日の夜には「私の班のみんなが感じたことをまとめると、おもに3つのことがあります」というように、活き活きした強い表現に変わってきました。
さて原爆資料館は、私自身中3の修学旅行以来40年ぶり。14歳のときに感じたのは衝撃と憤怒で、誰だか分からない相手にただ怒っていたし、作文に「こんなこと二度と起こってほしくない」という感想を書いた思い出があります。しかし、54歳の今回考えたのは、亡くなった方々が、死ぬ間際に何を考えていただろうかということです。そして、それはきっと「次の時代の子どもたちよ、生き延びてくれ。平和で元気に育ってくれよ」ということだったのではないかと想像しました。歳をとり親になったからこそでもあり、「オルゴォル」の解説を書くという出会いの中で「先人が未来の子を思った思い」の大きさを噛みしめたことが、大きかったと思います。
花まる学習会を始めて20年、ずっと心にひっかかっていたことがあります。それは、川口ふたば幼稚園の新藤たか子園長先生の思い出です。大学受験生を教えている中で、小学生を対象に「メシが食える力」「考える力」をつける教室を開きたいと考えているときに、夏の幼稚園児のお泊り保育のお兄さん役というバイトをした先で出会いました。夜の先生方との懇親会でその考えを言ったら、先生は「今どき珍しく気骨があるわねえ。うちでやりなさい」と言ってくれたのです。
秋になって園を訪ねたところ、道を隔てたご自宅に案内し、奥から数葉の手紙を持ってきて見せてくださったのです。それは、父君である栗林忠道中将(硫黄島の戦時の英雄)からの手紙でした。娘をたこちゃんと呼び、元気かと気遣い、しっかりがんばりなさいと元気づける内容でした。私がひっかかっていたのは、何故あのとき先生が、わざわざあの手紙を見せようとしたのかということでした。そして、それが今年解けたように感じました。それは「いのちのバトン」をしっかり次の時代に渡していってね、というメッセージだったのではないかと。
戦時の大人たちが平和な世をと願った未来が、今です。「まだ見ぬ未来の子どもたちよ」と彼らが想ったのが、私たちです。豊かにはなったけれど、墓参りもまともにやらない人が増えていく中、生き物としての生命力は落ちてしまったように感じます。気が遠くなるような数の先人の命の系譜として、一人の私がいます。メシが食える大人を育てる一歩目は、ご先祖様の思いを想像することなのかなと、酷暑の長崎の坂の上で考えました。汗をぬぐい海を見ると、海面がキラキラと輝いていました。
花まる学習会代表 高濱正伸