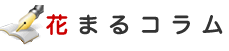『車椅子のI君』 2013年5月
小学校4年生のとき、I君という車椅子の男の子が、先生であるお母さんと一緒に転校してきた。I君が自分の力で動かせるのは顔と手首から上だけである。そのため車椅子は指で操作する電動式のものだった。
彼はとても物知りだった。休み時間になると誰も知らないような科学や歴史の話を得意げに話してくれた。私はすぐに彼と友だちになった。I君はどの授業にも積極的に参加した。体育の時間、サッカーボールを使う授業なら、顔の前に軽くトスしてあげればヘッディングができる。しかしこちらが不用意な投げ方をすると勢い余って転倒してしまう。習字の時間、前方に重心がかかりすぎて書いた字の上に顔ごと突っ伏してしまい、顔中墨だらけになってしまう。なかなかみんなと同じようにはいかなかったが、失敗を恐れずどんなことにも一生懸命に取り組んでいた。
お母さんも先生としての仕事があるからいつもそばにいるわけにはいかない。そういうときは私がお助けマンになる。鼻水が出たとき、ものを落としたとき、車椅子が脱輪して動けなくなったとき、I君は私を頼りにしてくれた。そんな中、「のぶちゃん、のぶちゃん、助けて。」と悲鳴にも似た声で私を呼ぶときがある。悪ガキのKがちょっかいを出しているときだ。顔や頭を小突いたり、上履きをとって外に放り投げたり、誰も見ていないときに犯行に及ぶ卑怯なヤツだ。I君は唾を吐きかけて応戦するが、そんなことではKもひるまない。やりたい放題やったあとは逃げ足が速い。そういうことが何度もあったが、彼は決して涙をみせることはなかった。
私はI君を「障がいがあってかわいそう。」とは思わなかった。不自由さの程度は違うが、自分だってやろうと思ってもできないことはたくさんある。同じように失敗もする。友だちとして、困っているから助けたし、自力ではできないから手伝ったにすぎない。
6年生になるとI君は休みがちになった。体調が良くないということだった。そして、正式なお別れもできないまま卒業を目前にして転校していってしまった。最終的には、普通学級で中学校生活を送るのは難しいという理由だったが、私は中学でも今までのようにやれば大丈夫ではないかと軽く思っていた。
中学に入学すると慌ただしい生活が始まり、だんだんと彼のことは記憶から薄れていった。それから一年半後の中2の給食の時間、突然担任の先生からI君の訃報を聞かされた。I君のお母さんからのメッセージも一緒だった。「H小で一緒だったみなさん、短い時間でしたが、Iはみなさんと過ごせて幸せでした。本当にありがとうございました。」
心の中に冷たい風が吹いた。その時初めて彼が余命短い難病を患っていたことを知った。彼は私とは比べ物にならないほど一日一日を真剣に生きていた。自由とか不自由とかではなく、生きることそのものに全力を傾けていたにちがいない。それなのに自分は生きていることなんて当たり前のことだと思っていた。いやそれすらも自覚しないまま、彼と同じ時を過ごしていた。なにか言いようのない虚しさと後悔にさいなまれた。
KARINBAの「HOMETOWN」という曲に、「どこまでも明日がつづくと思っていた」という歌詞がある。若いうちは時間は永遠であるかのように思える。歳を重ねるうちに限りある人生をどう生きようかと考える。どちらにしても幸せなことなのだ。
今、自分はI君のように日々精一杯生きているのだろうか。