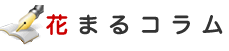『桜が咲くその日まで』 2014年5月
机を挟んでお互いが向かい合う。人と人。大人と子ども。先生と生徒。見つめる側と視線をそらす側。ただ、うつむいている。その目線の先にはノートが一冊。開かれたまま、机の上に置かれている。
「白紙」のノート。うつむきながら、それを見ている。言葉を投げかける。質問をする。返事はない。質問をすることは、やめた。沈黙が続く。やがて、「答え」の代わりに出てきたのは、涙だった。
溜まった涙が滴となり落ちる。好きなだけ、泣くといい。言葉にできないのであれば、代わりに涙を流すといい。自覚があるからこそ、涙は流すことができる。その「自覚」が心に宿ることを、ずっと、僕は、待っていた。
私には6歳上の兄がいる。その兄には3歳になる「さくら」という名前の娘がいる。こう見えて私はもう立派な「おじさん」なのである。兄たち家族は京都に住んでいるので、私はなかなか会う機会がない。その代わりに時々兄から「元気か?」という電話がかかってくる。当然、さくらちゃんのことも話題にあがる。
「親ってね、やっぱり欲がでるよ。お腹のなかにいたときや、産まれてきてくれたときは元気であったらそれでいいと思っていた。目が見えたらそれでいい。耳が聞こえたらそれでいい。五体満足でいてくれたらそれでいい。もう他には何もいらない。でも少しずつ欲が出てくる。周りと比べて何かが早いとか、遅いとか。極端な話、お前だって小さいとき全く喋らなくて人見知りだったのに、いまでは塾の先生っていう喋る仕事をしているんだから、早いとか遅いじゃなくって、その子なりの進むペースがあるってことはわかってるんだけどね。」
そういった欲は、私にもある。
「お!この問題ができている!ということは次の問題も・・・!」
「今週の確認テスト満点だ!ということは来週も・・・!」
私の欲は叶わないこともあるのだが、ついつい子どもたちの精一杯のがんばり、その子なりのがんばりをみていると欲を出してしまう。出てしまう。欲があるからこそ、「こうしたほうがいいんじゃないのかな」と言ってしまいたくなる。けれども、基本的には最低限のことしか言わない。言いすぎたら、強制になってしまう。その子が考える余地、工夫する余地がなくなってしまう。最終目標は「自分で、できないことをできるようにする」こと。そのために必要な創意工夫は、「今自分がやっていること」への自覚から生まれる。冒頭にあげた子がそうである。宿題を忘れる。言い訳をする。それが通用すると思っていた子だった。「それは違う」という自覚が芽生えることをずっと、ずっと待っていた。いつか必ず気づいてくれる日がくると、信じて待っていた。
「自覚」してから彼は、強かった。学習を飛躍させた。やり切る。工夫。主体性があるからこそできること。結果として、点数としても表れはじめる。それが自信にもつながる。まさに「自学」だった。
桜守という仕事がある。ある桜守が、北海道の桜が咲かない地域に桜を咲かせた。その桜守が行ったのは、桜の木を手であたためる、桜の木に声をかけるということだけだった。「寒いな。頑張れ。もうすぐ春だよ」と。
それだけのことで、肥料などの科学的な理屈では一切咲かなかった桜が、咲いたのだ。桜守と子どもたちと関わるこの仕事も同じだと思った。無理矢理ではなく、理屈でもない。寄り添って今のその子のがんばりを認めて、応援して、あたためていく。子どもは必ず伸びる。必ず大きな桜を咲かせる。その日まで私は子どもをあたため続けていく。両手いっぱいに、かかえきれないほどの愛情を携えながら。
片岡 上裕