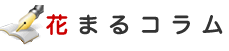『ビリギャル』 2015年8・9月
迷っていたのだが、話題の映画「ビリギャル」を観ることにした。迷っていた理由は、その奇跡のストーリーを連想させるタイトルである。塾講師を長くやっていると、偏差値を20、30飛び越えて合格することに特別な驚きはない。センセーショナルに、「学年ビリのギャルが1年で偏差値40上げて慶應大学に現役合格した話」とうたわれても、「へぇ、そうなんだ。がんばったんだね。」くらいの印象だった。以前にもお伝えしたが、今の大学入試は合理的な学習法と徹底した修練によって誰にでもチャンスはある。もちろん相応の努力ができることはすばらしいことだし、そこに向けた指導者の力も評価されるべきだが、それ以上の価値をこの映画に見つけることができるのだろうか、という迷いであった。
結論から言えば、いい作品だった。予想通りの展開ではあったが、随所に涙をふかずにはいられない場面があった。合格ストーリーの裏にある親子愛の話に心をうたれた。詳しい内容には触れないが、不器用な父親像と、子どもたちに無償の愛を注ぐ母親像が絶妙に描かれていて、こうした家族の構図は程度の差はあれ、どこにでもありそうな話であった。私自身も自分の考えをわが子に押し付けてしまったこともあったし、それを影で支えていた妻の姿も知っている。これでいいのかと思ったことも実は少なくない。子どもを育てることは決して簡単ではないし、思い通りにはいかない。迷いの連続だということもほんとうによくわかる。この映画を観て改めて思ったのは、「こうなってほしい。」という親の願いは尽きないけれど、「やっぱり最後は子どもを信じて応援することが親の大切な役割だな。」ということである。それはいつも講演会でお伝えしていることでもある。
もう一つ、この映画の価値を見つけた。それは、上映終了後に、「わたし、もうちょっと勉強がんばろうかな。」「慶應、受けてみようかな。」という前向きな会話をしながら帰っていく高校生らしき若者の姿だ。原作者の坪田信貴氏の指導はまさに「ナナメの関係」を使った指導そのものだが、この映画自体が持つメッセージ性が同じような役割を果たしているような気がする。この映画から彼らは勇気をもらったにちがいない。そうしたキラキラした若者を横目に見ながら、「来年は慶應受験者が増えるかもしれないな。」と思ってしまうのは職業病であろう。
結局私は原作も買ってしまった。そこには、映画では表現できなかった、さらなる人間模様が描かれていた。母親が葛藤する場面ではまた涙した。坪田氏の教育者としての哲学、指導法にも感動したが、主人公の成長過程と照らし合わせると、「よく受かったな。」というのが率直な感想である。彼女自身の努力は並大抵ではなかっただろう。その意味では奇跡のストーリーとしての読み応えがある。
「どんな子どもにも可能性がある。大人がその可能性を信じつづけること。」 初心にかえるよい機会だった。