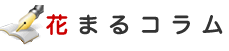『芯をもって』2016年3月
私は高校から音楽学校に通っていました。高校3年生の学期末に行われた実技試験でのこと。試験が終わり品評を聞きにいくと、「音に芯がほしい」と言われました。
校内新聞のコラムの中で、世界的に有名な室内楽奏者の原田幸一郎さんが、「ジュリアード音楽院での生活は、飯とトイレ以外はヴァイオリンしか触らなかった。人生に一度はそういった時期がなければならない」との一節あり、その言葉が私の心にとても引っかかりました。
当時の私は、音楽に没頭するという生活とはほど遠いものでした。家にも帰らず、経済的にも完全に親の脛をかじる様な生活をして、生ぬるい環境でした。16歳の自分の中では順風満帆の日々を過ごしているつもりでしたが、母に会う度「地に足が着いてない。」と言われました。
大学に入り数ヶ月が経ちました。「芯がある音」とは何か、日々模索する中で、精神的自立だという事に気が付き始めました。環境を変えたいと思う様になり、自分の師匠に留学の相談をしたところ、自立を求めた留学に賛成してくれ、すぐに現地の先生を紹介してもらいました。そして気が付けば思い立った3ヶ月後には現地にいました。
自立を求めて渡ったパリで実践したのは、「ご飯とトイレ以外はチェロしか触らない」生活。音楽に没頭する、孤独と向き合う、まさにそんな日々が続きました。
初めての一人暮らし、更に異国の地、言葉も通じず葛藤の毎日でした。あげくタイミングが悪い事に、父親が仕事を退職。家庭は経済的に苦しくなり、母が日夜働き始める様になりました。妹から疲れていく母の様子を聞き、とても胸が苦しくなりました。
しかし学生の身分で経済的に自立することはできず、母は一言「お金の事は心配しないの。アルバイトするぐらいだったら練習をしなさい。勉強は今しかできないのよ」と励ましてくれました。
パリでの暮らしは極貧生活で、一年間で外食はたったの2回。毎日パンにハムを挟み持ち歩き、電車賃もままならずチェロを担いで何駅も歩くのが当たり前の日々でした。
そして孤独な毎日は、次第に明るく日常を過ごす人たちへの嫉妬となっていきました。一人で音楽に向き合う事を決めた私は、家族とも友達とも一切連絡を絶ち、誰とも話さずチェロに打ち込む生活を一年続けました。いつしか顔の筋肉が落ち、笑うと頬が痙攣するようになっていました。
しかし、どんな事があっても、努力を続けられたのは「頑張っていること」が唯一、母に顔向けできることだったからです。張りつめた気持ちの中で、自分を支えてくれたのはまぎれもなく家族という存在だけでした。
そして生き方の全てが音に繋がるという事を疑いませんでした。嬉しい事も辛い事も含め一生懸命生きる事が、豊かな人生になり、美しい音に繋がっていくと信じていたのです。
パリでの生活は不自由だらけで、決して日本の様に安心、安全、便利ではなく、とても質素なものでした。しかし私はそれをいつしか幸せだと感じる様になりました。まさに、「地に足をつけて生きる」という事を体感していたのだと思います。
パリ留学から3年後。日本に帰国してから最初の仕事で演奏をした時、聴きにきていたピアニストの方が「音に芯がある」といって下さりました。私はその言葉が何よりも嬉しく、努力が報われた気がしたのです。
子どもたちが自分自身に向き合う事は、もしかしたら私の様に大学生になってからかもしれません。いつになったとしても、とことん向き合い切るということで、初めて自立への一歩を歩みだせるのではないでしょうか。自分自身と向き合い続けた、艱難辛苦の留学時代、それが今の私の財産です。
笹森 壮太