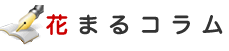『幸福な時間』2014年5月
こんにちは、2014年度も引き続き、年中~小学校3年生ぐらいまでの「赤い箱」―いわゆるオタマジャクシ時代―の子どもたちの成長を見つめながら、花まるメソッドを知っていただくための連載を担当します。また一年間よろしくお願いします。
さて、第一回目は僭越ながら、私自身のお話を。
読書と工作と絵画が大好き。ただ、学校では一度も手を挙げたがらない、内気で引っ込み思案の典型のような子どもでした。通知表にも「積極的に意見が言えるといい」と書かれるのが通例で、小学生時代「もっともなりたくない職業」―そんなことを考えるのも変ですがーが、「先生」と「歌手」でした。とにかく、人前に出て注目を浴びることで、緘黙状態になってしまうのです。背の順はいつも一番前。そのうえ鼠径ヘルニアとアトピー持ちで病院通い。クラスで最初に風邪をひき、そのまま中耳炎になり、しばらくほとんど耳が聞こえなくなる(以下繰り返し)という身体の弱い子でした。夢見心地に一人の時間を満喫することが至福の時間だった本人にとっては、耳が聞こえるかどうかは、あまり重要ではなかったらしく、その事実は、後から幼稚園時代の連絡帳を読んで知りました。今では社内でピラティスを教えるくらいで、体を大切に管理することにかけては、人一倍関心があるのですが、もしかしたら「自分は人よりずっと努力しないと健康な体を獲得できない」という恐怖心の名残があるのかもしれません。
世界が、幸福と、試練に満ちていたあの頃のこと。
補助輪がとれたばかりの自転車に乗って15分。草きれの立ち上る庭をうっとりとしながら抜けるとそこは、縁側から入る一軒家のアトリエ。おじいちゃん先生が、適度な距離で、しゃべらない私を受け止め、大好きだった絵画工作を存分にさせてもらえたあの空間は、今の創作活動の原体験です。
何でもない日のプレゼントが本だったこと、母と妹と3人で原付に乗って図書館に行く習慣は、読書は一生の友であり、師であると教えてくれました。父方の祖父にもらったグリム童話集は、暗記するほど何百篇も読み、母方の祖父から譲り受けた古い本たちは、クシャミと戦いながらも、毎晩のベッドのお供になります。何よりも母国語の持つ豊かな表現を愉しみ、さらに見も知らぬ外国の文化や習慣に興味をかきたてられ、読書を通して追体験をしていたのも、あの時代でした。
高学年になり「もっと勉強をしたい」と母に直訴する頃には、確固たる意志を持つ子どもになっていました。自分だけの時間を追求する時代は、ここで終わりを告げます。その後私の意識は、外へと向かい始めたからです。「コンプレックスは強みになる」という言葉がありますが、一番苦手なものにこそ挑戦し、自信をつけていくこと、それが大人になることだ、と子ども心に感じていたのです。
幼少期から長い期間、殻を破ることもせず、ただ自分の世界にひきこもっていた(幸せな)時代。その記憶は後に、のびのびと自分の「やりたいこと」だけに没頭できる時間をくれた両親への、感謝の思いに変わります。不覚にも、あの頃一番なりたくなかった職業に今はなり、本当に大好きだったことを、ライフワークにしています。
今思えば、あれだけ濃密な、自分だけのじゆうな時間に代わるものなどなかった。
二十歳になったあとの時代に、いろいろな局面で、意味のあることだけをしたいという感覚を信じ、納得いくまであきらめない強い意志を貫き通せているのは、なぜなのだろうか。
きっとあのじゆうな時間と、「自分は愛されている」という自信だったのだなと思います。弱くて身体も小さく、人前に出たがらないわが子を、決してそんな風に形容することなく、「ママの可愛い由実」「大好きな由実」と話しかけ、何でも大げさに喜んでくれたあの頃の親馬鹿な母に、感謝しています。もちろん父にも。
どんな子にも秘めた種があって、その芽は必ず花を咲かせるのです。大人になった彼らに、大輪の花を咲かせられるのは、幼児期の幸福な時間と愛されていたという自信です。