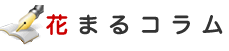『HOT MILK』2016年6月
私は小学六年の時に、中学受験を経験しました。中学受験というのは決して楽なものではありません。最初から受験をするつもりではなかったとは言え、一年生の時から通塾を始め、六年生のころには週に五日、母の作った弁当を食べることだけを楽しみに塾に通っていました。放課後、友人たちと遊ぶことや、休日に家族と旅行に行くことなど、ゼロではなかったにせよ、ほとんどそうしたこともできませんでした。
しかし、そうした涙ぐましい努力にも関わらず、結果というのは残酷です。あれほど私が一番行きたいと願った学校は、不合格だったのです。
合格発表会場からの帰り道は、悲しいというよりは呆けたような気持ちで、泣くこともなく帰ってきました。自分の心の中で「この何年間かの頑張りはいったい何だったのか」「こんなことなら、勉強なんかしないで遊んでいればよかったではないか」そんな想いを何度も何度も、反芻しながら。
自宅に到着し、結果を家族に淡々と報告。私は平静を装っていました。というよりも、自分の中では平気なつもりでいたのです。食事もいつもと変わらずとり、風呂に向かいました。そして、風呂から上がり、灯油のストーブの前に座ったその時でした。なぜかいきなり涙があふれ、止まらなくなったのです。堰を切ったようとはまさにこのことでした。
私としては気づかれていないつもりでしたが、母にはお見通しだったのでしょう。慌てる様子もなく、母は一言、
「ちょっと待っときや」
と言って、台所に向かい、数分後、手に何かを持って戻ってきました。それは、少し甘い匂いのするホットミルクでした。
「これ飲んだら気持ちが落ち着くねんで。」そう言って飲ませてくれたホットミルクには、ほんの一滴のブランデーがたらされていたのです。それが甘い匂いの正体でした。
「あんたはよう頑張った。お母さんは見てたから知ってるで。」
それを飲みながら、母に背中をさすられていると、余計に申し訳ない気持ちがしてきて、また涙が止まらなくなりました。灯油ストーブのにおいと、いつもはにぎやかな家のひとときの静寂、そして私の背中をさする母の手のぬくもり。その時のことは、忘れることができません。もし、母がこの時、第一志望校に合格できなかったことを責め立てたりしていれば、私は一生中学受験をしたことを後悔していたことでしょう。しかし、母は、私が「頑張った」「やり抜いた」ことに賛辞を贈ってくれました。結果ではなくて、そこに至るまでの道のりに寄り添い、認めてくれたのでした。そのほんの数分の出来事が、私にとっての受験を幸せなものにしてくれました。そしてその数分は、今も私の宝物です。
私もまた、あの時の母のような目線で子どもたちと接していこうと思います。子どもたちに限らず、人というのは自分が「頑張っていること」を誰かに近くで見ていてほしいものです。逆に言えば、その「見守られている感」があれば、人はどこまでも頑張っていけるものなのかもしれません。
子どもたちが、ふとしたことで「自分はダメだ」という思いにとらわれ苦しんでいることがあれば、私は声をかけたいと思います。「よく頑張ったね。先生は知っているよ。側でいつも見ていたよ」と。つらい気持ちがふっと穏やかになった、あの日、母が私に飲ませてくれたホットミルクのような言葉を。
西川 文平