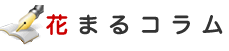『教育者とは』2018年2月
「教える」ということを仕事にしていると、愛情だけでやれることはこの世界にはないなと感じます。子どもたちに、一人で生きていく力をつけさせるために、彼らの世界と生態をよく知っていて、さらに育てる技術をきちんと持っていなくてはならない、一個の職業人でなければならない、と。
目の前にいるのは小さな人たちですが、ただ年齢が小さいからここにいるだけで、子どもの方が劣っている、というわけではないのです。むしろ、「この人たちは、自分をはるかに超えて、未来を創っていく人なんだ」という敬意を持って、子どもという宝物に接しています。
高いものにあこがれ、自分を成長させよう、前進させようとひたむきに願い、伸びよう、伸びたいと思っている彼らのそのセンサーは、まっすぐに目の前にいる大人をとらえ、その人の中の「伸びよう」という気持ちに反応します。
初々しい感動、新しい命のようなものが、その人の中にあると、子どもたちはひきつけられるのです。彼らの世界の人間であれるかどうか、よりよい自分を目指しているかどうか、がいつも問われる。
同級生に知的障がいのある男の子がいました。喋らない子どもだった当時の私は、彼が何をしているのか、声はかけませんが、いつも注意深く観察していました。
年長になったある日のこと。担任の先生はある出来事を、彼のやったことだと判断しました。口の中に絵の具を入れてしまうような子だったので、先生の推測は正しいようにも思えました。ほかの先生と話すその内容を聴いていた私は、「それはちがう」と思いました。事実は違っていたのです。ただ泣いている彼にそれを証明する手段はないように思えました。もしかしたら、私だけが真実を知っているのかもしれない。生まれてはじめて、正義感のような何かに突き動かされた私は先生に訴えました。すると先生は、「ありがとう、うれしい」と言ってくださいました。「あなたがいてくれなかったら、彼にもっと苦しい思いをさせていたと思う」と。そのように言葉にしてわたしに伝えてくださったことは、私の原点のひとつとして刻み込まれています。
大人と子どもであるということ以前に、一個の人間として目の前の人を尊重することの大切さを、先生の姿に見たのです。それは、子どもであるわたしと、その時傷ついていた彼に、大人に信頼されることの喜びを与えました。正しいと思うことを信じる勇気も。
人間は、小さなころから実はそんなに変わらないものです。自分がもともと持っていた、一見意味をなさないかのように思える子ども時代の感覚は、実は、人生を進むために最も重要なコンパスなのです。だから大人になったらその後は、いかに自分だけの子ども時代の感覚を取り戻し、本来の自分を知っていけるかが大切なのでしょう。いろいろな価値観から自由でないとその人本来の姿にはなれませんし、人がその人自身になることを極めていくと、必ず人の役に立つことができるのです。そして、それこそが、自立している一個の人間ということでしょう。
2018年も、教育について真摯に向き合う集団でありたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
井岡 由実(Rin)