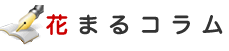『父を送る』2021年5月
病床にある父を元気づけようと囲碁の元名人の方をお連れして、人吉の自宅で一局指導碁を打っていただいた顛末を書いたのが、ちょうど3年前。この3月に、その父が逝きました。昭和3年生まれの92歳。大往生と言ってよいでしょう。体は弱っても、囲碁のおかげか頭は明晰で、亡くなる2日前にも電話をしてきて、「お前は無理をし過ぎるところがあるけん、体だけは気をつけなんばい」と言われたのが、遺言となりました。
3年前にも書いたのですが、私と父との関係は少々ギクシャクしていました。3人姉弟の末っ子である2歳下の弟は、外見的にもハンサムで可愛がられるタイプ。父にまとわりついて「タバコの煙の輪っかを作って」とせがんでみたり、膝に入ってゴニョゴニョ甘えたりしているのですが、私はとうとう一度もその膝に入れませんでした。自分から行けばよいのですが、勝手に拗ねきってしまっていたのです。1年生くらいのとき、何かの拍子に「どうせお父さんは、まーちゃん(自分のこと)なんか可愛くなかとやもん!」と叫び、襖をバチンと閉めて風呂場に駆け込んで、泣いていたこともあります。
そういう関係を不憫に思った母に諭されたのであろうことは間違いないのですが、3年生のとき、急に母が「お父さんとキャッチボールでもしてくれば」と言い、見ると父が一度も持ったことのないグローブを持っていました。私の顔はこわばっていたと思います。親子ともどもぎこちないキャッチボールが始まりました。通りがかった高校教師で近所の習字の先生が、「親子で良かですなー」と言うのですが、作り笑いをしながら内心は「早く終わらないかな」という落ち着かない心境でした。ただ、心の奥では、それでも嬉しい気持ちがあったことも覚えています。
10年前くらいになるか、『文藝春秋』で父との思い出を執筆してくれという依頼があり、そういうありのままを書いたことがあります。すると、文春の定期購読者である父からすぐに電話がかかってきました。「読んだばい。可哀そかことばしたね。自分に父親がおらんだったけん、どぎゃんしたらよかかわからんやったとたい。悪かったね」。せっかくの詫びなのですが、当時の私はまだシコリというのか「今頃言われてもね」とこだわりが取り除けなかったのです。
ただ今回、具合が悪いと聞いて駆け付けたときには亡くなっていたのですが、顔を見て驚いたのは、あどけないという言葉がぴったりの、赤ちゃんのような表情だったことです。嬉しそうにすら見えました。お彼岸に亡くなった人は、愛する人がお迎えに来たのだという言い伝えがありますが、まさにお彼岸の日に旅立った父は、きっとお母さんがお迎えに来たのだろうと思いました。
というのも、4歳ごとに離れた男ばかり4人の兄弟の末っ子だった父は、早くに父を亡くし、女手一つで育てられたのでした。溺愛されたことは想像に難くなく、私の伯父に当たるお兄さんの一人は、生前「悦男は可愛がられよったもんなー」とよく言っていました。この子だけは戦争に取られたくないと、医師を目指すよう促されたそうです。この数年、本家の墓に入ることをその家の長男に懇願していたそうで、その理由が「おふくろと同じ墓に入りたい」ということだったと聞きました。ザ・マザコンというのか、92歳になっても世界の誰よりも母を慕い続けたのでした。
私にも、化学反応が起きました。普段、子育てに悩んでいる両親の相談をたくさん受けている経験があったおかげでしょう、母のお迎えに喜ぶような無垢な表情を見た瞬間、「あ、自分に父がいなかったことで、男親としてどう接してよいのか、本当にわからなかったんだな」と、実感として想像できたことです。シングルマザーの息子あるあるというのか、親となったときは、若い多くの父親同様かそれ以上に戸惑うことも多かったんだろうな、と。人間として普通のことではないか。そう思えたとたん、長年の澱のようなわだかまりが雲散霧消してしまうのを感じました。
もともと20代で迷走のやりたい放題の時を過ごそうが、医師を継がなかろうが、「生きていればよい。親より後に死ねばよい」と、自由にさせてくれ、文句の一つも言わない親で、基本的に感謝してはいたのですが、幼少時の心の傷跡が一つだけ残っていたのが、消えました。
さて、私との関係は微妙でしたが、長年続けた町医者としての世間からの信頼は厚かったようで、コロナ禍で、家族葬として開いた葬儀はたくさんの花であふれました。数名の知人に「花を贈ろうと思ったんだけど、『もうこれ以上、町のどこにも花がない』って言われた」と教えてもらうほどでした。
また、焼き場に向かう前に、霊柩車で関わった場所を回ってくれるのですが、自宅や医院跡、入院していた病院はよいとして、妻(私の母)の入っている介護老人施設は「霊柩車が敷地に入るのを嫌う人もいるから、道路からになると思う」という事前の葬儀社の話でした。しかし到着してみると、門から中に入れたばかりか、車椅子に座りひざ掛けをした笑顔の母を先頭に、医師や看護師も含むスタッフの皆さんが玄関前にズラリと並んで見送ってくださいました。小さな町の医療の先輩への最敬礼だったのでしょうか。そのことも嬉しかったでしょうし、認知症の進んだ母のことを父はいつも心配していましたから、きちんとお別れができたことを喜んだと思います。
年長の側から亡くなるのは、自然の摂理ではあります。「ありがたい関係に包まれた、素晴らしい人生でしたね。育ててくださりありがとうございました。私もシングルマザーの孫として、与えられた時間を誠実に生ききります」と、骨片を拾いながらつぶやいていました。実は、私は骨壺に入れる作業は初めてだったのですが、「メメント・モリ(死を想え)」の言葉が染みるというのか、ズドンと感じることもありました。昭和一桁生まれでありながら180 cm以上の大男で、昔の集合写真では一人だけ胸から上が抜けているような父でしたが、崩れずにそびえ立って残った真っ白な大腿骨と丸い骨頭の印象が、心に焼き付きました。そして、「うん、必ず自分にもその時は訪れる。悲劇ではない。全員に平等に。最後に悔いが無いようによく生きねばな。次世代を育てることに全力を尽くそう」と何度も何度も思い返しながら、飛行機の窓からの景色を眺める帰京となりました。
花まる学習会代表 高濱正伸