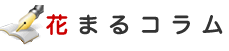『知識と暗記』 2025年1月
『言語の本質――ことばはどう生まれ、進化したか 』(共著・中公新書)、『算数文章題が解けない子どもたち――ことば・思考の力と学力不振』(共著・岩波書店)などの著者である慶應大学教授の今井むつみ氏の新刊『学力喪失――認知科学による回復への道筋』(岩波新書)が昨年9月に発刊されました。この本の冒頭で今井氏は「学習性無力感」に陥っているのは、子どものせいではなく、大人のほうに基本的な誤解があり、子どもたちの学ぶ力を喪失させているのではないかと述べています。
先日川崎市の小学校で行った私の講演会(子どもがやる気になるシンプルな子育て)でも、この「学習性無力感」についてお話しする機会がありました。「学習性無力感」とは、自分ではどうすることもできない不快な刺激を与えられ、強いストレス状況下に継続的に置かれたことで、「あきらめ」を学習して無力感を抱いた状態のことを言います。もともとやる気がなかったわけではなく、学習上の努力に結果が伴わないような経験を積み重ねたために、本来解けるはずの問題に対しても「どうせ解けない」「何をやっても無駄」と認知し、ますますできなくなってしまうという悪循環に陥ることです。とにかく「勉強はきらい」の状態です。私の講演会では、やる気・意欲にはいくつかの段階があり、そのなかでも「勉強はきらい」にさせないためにご家庭で何ができるのかについてお話ししています。詳細は紙面の関係で割愛しますが、所属小学校での講演会開催にご関心等ございましたら、 花まる講演会ホームページ 講師プロフィールをご参照ください。
さて今井氏が指摘する大人の誤解についての一例を引用します。
子どもの学力不振の原因となっている大人側の誤解に、教育についての信念がある。この信念は、知識と記憶についての誤解に起因するものである。知識は客観的な事実の集積で、それをたくさん覚えるほどよい、というエピステモロジーをもっていると、必然的に知識は教えられて覚えるものだという信念につながっていくのである。すると、子どもたちは、知識は自分でつくっていくものではなく、効率よく教えてもらえるものと思うようになる。つまりは、学びに対して受け身になってしまうのである。
また、この知識観をもっている教え手は、わかりやすく教えれば子どもたちはわかるはずだという信念ももつようになる。できない問題は繰り返し解く練習をすればわかるようになるはずだ、できないのは、子どもたちのやる気や集中度が足りないからだ、と思うようにもなる。
今井 むつみ『 学力喪失――認知科学による回復への道筋 』(岩波新書) (Kindle 版 p.58)
※エピステモロジー…知識に対する認識
同書は学校の先生向けに書かれているところも多いのですが、私たち塾講師にも大切な示唆を与えていると思います。子どもたちが常に受け身の状態では、そもそも個々にどこまで理解できているのか、教え手が把握できません。目の前にいる子どもたちは前提となるスキーマ(経験から導出した暗黙の知識)にも違いがあります。単なるわかりやすい授業、楽しい授業だけでもだめなのです。その段階でその子らしい参加ができる授業でなくてはなりません。
また、「プレイフル・ラーニング」(遊びを通じて学ぶ)の一節では、アナログ時計を読むことに苦労していた小学校低学年の子どもたちに、今井氏の研究室で「時計カルタ」を考案して試したところ、キャーキャー言いながら夢中で楽しんだと言います。スクールFCの「カルタ」も5年生以降で覚える社会や理科の膨大な知識の暗記に苦労することを見越して、事前にゲームを通じて楽しく身につけられるように開発した教材です。みんながそれぞれの形で参加できる授業を目指しているわけです。
教育者向けの専門性の高い内容も含まれている本ですが、日々の生活のなかでできるようなことも書かれていますので、気になる方は一度手に取ってみてください。
いよいよ本命校の入試本番という方も多いと思います。毎年書かせていただきますが、受験の世界には「受験当日まで伸びる」という言葉があります。私自身も試験直前の一週間が一番伸びたという実感があります。実際に本番直前から当日にかけて急成長する受験生の姿を何度も見てきました。最後の入試が終わるまで、あきらめることなく、その可能性を信じて挑戦してほしいと願っています。
スクールFC代表 松島伸浩