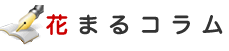『自由研究』2025年2月
先日、某大手出版社の「小学生の夏の自由研究(正確には子どもたちが作る図鑑・自由研究・自分ノート)」の最終選考会で審査員を務めました。昨年に続いて2回目なのですが、応募総数も数千件と一年で14倍に増加し、内容の充実ぶりたるや驚くものでした。昔の自由研究といえば、「いろいろな形のどんぐりを集める」というようなのどかなものが主流だったと思いますが、テーマも実に広くバラエティに富んでいて「宝石」「既存の図鑑にない古代鮫」「地下鉄」「沖縄」「マンホール」「心臓」「学校のひみつ(教師の仕事の現実)」「千羽鶴」「山の空気」「スイカの種」「剣道」「PTA」「霜柱」「おかあさん」「車いす」などなど、本当に多様でしかも一つひとつが小学生離れした深掘りぶりで、感動しました。思うに「博士ちゃん」というテレビ番組がおもしろく親子一緒に楽しめる内容で評価も高いのですが、その人気と影響で一つのことを大好きで探求することの価値が子どもたちに浸透しているのかなと推察しました。
一方で、昨年私の教え子たちからも考えさせられる事例がありました。一人は中一のKくん。2023年の「高濱先生と行く修学旅行」に参加した子で、その時点で全国のロボコンで優勝した男として一目置かれていたのですが、中学生になった昨年は審査員の側になったので動画を観てほしいという連絡が来たのです。サマースクールに来たときのことはよく覚えていて、「目力が突き抜けているな」と感じたら、ロボコン優勝者との情報。なるほど技術の戦いで全国制覇するほどになると、こんな目になるんだなと思ったものです。そして審査員としての姿からは、背も伸びたくましさを増し、自信をつけて大好きなプログラミングと工学をさらに追究していることが伝わってきました。
もう一人は開成中二年生のAくん。スーパー算数で教えた一人ですが、学園祭用に映画を作ったから観に来てほしいと言う。映像制作が好きだという噂は聞いていましたが、私は講演会があり行けませんでした。すると動画を送ってくれました。それを観てビックリ。出演者(同級生)の演技のかわいらしい緩さこそあれ、カメラワークは中学生離れしているし、展開のおもしろさやテンポ・間など実に素晴らしい。上質なミュージックビデオを観ている感じで、プロとしてすぐに仕事ができるのではという水準だったのです。驚いたのは上手につけたなと感じた音楽についてで、誰の作品なのかと聞いたら、なんと「AIで作りました」とサラリと答える。新しい時代なんだなと感じました。
冒頭の自由研究もそうですが、これらの事例に共通するのは、自分が心から好きなことや関心を持ったことについて、ひたすらに探求し研究することが、喜びや自信となってその子ども時代や青春時代を輝かせるということです。そしてそれは将来に向かって心と頭を育てる大きな力となり人生の支えとなるでしょう。
目先の利益にとらわれず一つのことを追究することは、もともと芸術家やアカデミックの研究者たちが実践してきた生き方ですが、YouTube時代、つまり個々人が放送局として各々発信できるいま、新しい光を放っていると思います。たとえば歴史を愛しすぎた深井龍之介さんたちが北九州から発信している「コテンラジオ」がそうですし、山や自然が好きすぎる春山慶彦さんが福岡市で創作した独自のアプリ「YAMAP」もそうです。どちらも本当におもしろく、興味深い知的喜びを提供してくれます。大都会にあるテレビ局が情報発信を牛耳っていた時代は終了し国民総放送局状態のいま、住む場所にはまったく関係なく、独自の関心を見つけそれを深く掘った人たちの個性が注目もされ世界を変えるのです。
すでに大人の世界でも新世界の扉は開かれているのですから、子どもたちにはぜひとも自由研究の意義を伝え、のめり込んでもらえるような指導をしなければなりません。そのために大事だと私が思うのは、その意義を「言ってきかせる」こともそうですが、それだけではなく、まずは大人たちが実践してみせることです。実践して大人こそその喜びを体感し、のめり込む背中を見せる。これ以上の教育はないでしょう。
ちょうど先日、作文コンテストの優れた作品を掲載した「花まる作文」の巻頭文でも、同じような視点のことを書きました。「メシが食える大人になるために『自分の心を見つめる作文』を書くことを重視しています」と言うと、「良いですね」と言ってくださる方は多いですが、芯の底からそれを信じるならば、まずは大人こそ口だけではなく日々の行動として実践しなければならない。だから花まる学習会では、せっかく縁があって入社してくれた若者が本当に実力をつける最高の方法として、毎月一回のコラム書きをルールにしています。何かを教えてもらう研修よりも、主体的で人に発表し見てもらうコラムは、内省と思考をうながし、間違いなく力量をあげ、本人の幸せ感と自信につながっていると感じています。
わが子に確かな「生きる力」をつけたければ、子どもに身につけてほしいと信じる課題を、まずは親こそ行動として実践してみせることが大事。その課題は無数に考えられますが、何でもよいので関心を持った事象について探求や研究を楽しみ、日々の思いを文章にする習慣を喜びとすることで、子どもたちに良い影響を与えたいですね。
花まる学習会代表 高濱正伸