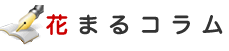『みかづき』 2018年11月
小学校の用務員が、用務員室に放課後訪れてくる子どもたちの勉強をみてあげるうちに、その教え方のうまさが評判となり、運命ともいえる女性との出会いから塾を立ち上げるという小説、森絵都さんの「みかづき」が、来年NHKでドラマ化されます。森さんの作品は中学入試では常連であり、この「みかづき」も昨年の中学入試で複数の学校で出題されていますので、ご存知の方も多いかもしれません。
直木賞作家である森さんは、児童文学を得意としていますが、ジャンルやモチーフにとらわれない絶妙な人間模様を描いたその作風が、幅広い読者層から支持を得ています。
「みかづき」も、塾を経営する大島五郎とその妻明子、その家族や従業員の人間模様を描いたフィクションですが、あまり知られていない塾業界の裏側を詳細に描いた小説はこれまでにはありませんでした。その意味では、舞台となった昭和後期から平成にかけて塾業界で生きてきた私にとっては、うれしさもあり、また怖さもありました。次々に起きる事件や事故、ニュースにはリアリティがあり、良くも悪くも過去の記憶と重ね合わせてしまうシーンがたくさんあったのです。
実際に1990年代から2000年初頭にかけて、「ゆとり教育」の名のもとに、「学校内での業者テスト廃止」「学習内容の3割削減」「学校週休2日制」など、国の政策に翻弄されたのは、子どもや保護者でした。通知表の評価が相対評価から絶対評価へ移行されたとき、1人の中学生(男子)のお母さんが目を赤くして私の教室にやってきました。中学3年生の保護者面談で、「内申点が届かないので、希望の公立高校の合格は難しい」と言われたというのです。中学2年生までの通知表は、さほど悪いものではありませんでした。このままいけば、第一志望の公立高校合格は可能な範囲だと思っていました。しかし、担任が変わり、絶対評価になったその年の1学期の通知表で、複数の教科の評定が下がってしまったのです。塾関係者の間では、絶対評価に変わればむしろ全体的に評定は上がるのではないかと言われていたのですが、この生徒に限っては違っていました。入試の合否判定で内申点の比重が高い高校を受ける場合、内申点が1点下がるだけでも受験校を変更しなければならないケースがあります。この子の場合は2ランク以上下げないと安心できない状況になってしまったのです。さらに担任の先生からすすめられた私立推薦の話に、お母さんはまったく納得できず、悔しさと戸惑いでパニックになり、面接が終わったその足で塾に駆けつけたのです。たしかに学校の先生の受けはよくないタイプの子でした。忘れ物も多く、提出物もあまり出さない。人の意見に左右されずいたってマイペースな性格。授業中にわざとオナラをして友達を笑わせたり、屁理屈を言って先生を困らせたり、学校では変わり者として見られていましたが、少し幼い面があるだけで心根はとても優しい塾では人気者の一人でした。勉強面では、公開模試で最難関校を狙えるほどの成績をとっていたので、通知表とのギャップはだれが見ても明らかでした。お母さんとしては、塾での成績は悪くないことを伝えるために、模試の結果を面談に持参していたのですが、見てもらうことさえできませんでした。「業者テスト廃止」を受けて、模試の結果を進路指導の参考にしてはいけないことになっていたからです。母子家庭の長男だった彼には公立に進んでもらいたいという親の願いもあったのですが、彼の将来を考えるとやはり実力に見合った高校に進学させたいということになり、担任の反対を押し切って、当日の試験の点数だけで合否が決まる私立一本に絞り、第一志望の私立高校に進学したのです。その後は早稲田の大学院から研究者の道に進んだと聞いています。
「学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在」という言葉が、「みかづき」の中に出てきます。学校という光がなければ、夜に輝くことができない塾。それでも月の光があったことで前に進むことができた家庭も確実に存在していました。ただ理想と現実の間で教育行政に振り回されてきたのは学校の先生たちも同じだったと思います。
事実上国が学習塾の存在を認め、学校教育との共存に方針を転換したのは1999年のことです。今では花まる学習会をはじめとして、学校と連携して学習支援をする塾が全国に広がっています。わずか20年で信じられないほど塾と学校の関係は変わりました。もしかしたら、人間が月に気軽に行ける頃には、学校の先生が塾で教えていても不思議ではないかもしれません。規制の枠を超えて、子どものために互いに学び合い、真の協働ができる日が来ることを切に願っています。
スクールFC代表 松島伸浩