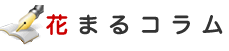『世に出て、生きる力になる』 2018年10月
“自分事”として学習をとらえる子どもは、課題のプリントを渡した瞬間に「なに?これ」と興味を持って食らいつく。そういう子どもは、学習の土台ができている。自然に面白がって取り組む子は、何もないところから自分で遊びをつくりあげる経験を積んでいる。もっといい遊び方はないか。どうすればもっと面白くできるか。遊びに対する貪欲さの原体験が意欲や向上心の源になる。
この時代、自由に外遊びをさせるのは難しいが、子どもは本来どんな環境でも自分で遊びをつくって楽しもうとする。自主性を育てたいなら、子どもの自由な遊びに親が介入し過ぎないことだ。困っているから手を差し伸べるのでなく、困っているから何とかしようとする子どもを見守る。子どもが退屈したり、騒いだりするのを避けるために、要求されるままに、ゲームやおもちゃを与えるのではなく、子どもがつまらないと感じているところから、子ども自身が遊びを考えようとするのを待つことも大切だ。例えば、最初は親が遊び上手になって、子どもと遊んであげながら手本を見せる。子どもが主体的に取り組むように、導きながら遊んであげることを意識してみることだ。
ブロックで何かをつくるとき、手本となる完成形の写真をどのタイミングで見せるかも、工夫が必要。最初から手本を見せず、自由な発想でつくらせたほうが熱中する子どももいれば、手本を見ながら、それに近づけていくのが楽しいと感じる子もいる。何もないところからつくり始めて、ある程度経験を積んだところでヒントとして手本を見せてもらうと、やる気を加速させる子どももいる。一人ひとりの特性や遊ぶ力を見極めた上で、それに合わせて引き上げ方を工夫する。
手取り足取り教えたことは、子どもが自分で考えてやってみようとする機会を奪うことになる。どこまで手本を示すか、どの程度までやり方を教えるか。そのさじ加減こそ、教育の難しさだが、肝でもある。さじ加減も経験。うまくいかないことを積み重ねていい具合を探る。つまり、子どもが面白がって能動的に取り組む方向が、基本線だ。学習も同じ。親や先生にやらされているものである限り、確かな学力は身につかない。自分で考え、能動的に掴み取ったものしか自分の中には残らない。当事者意識を持って主体的に、“自分事”として学習に取り組むことができて初めてそこに到達することができる。
“自分事"として学ぶということは、自分の学び方を自分でつくっていくということ。子どもたちに漢字の書き取りをさせると、「先生、書き取りは何回すればいいのですか?」と聞いてくる子どもがいる。何回書けば覚えられるかは、人それぞれに違う。3回書いただけで完全に覚えてしまう子どももいれば、100回書いてようやく間違えずに書けるようになる子どももいる。持って生まれた能力は、違う。自分に必要な回数は、子どもが自分自身で見極めるしかない。自分の能力を見据えて、自分の学習を自分でつくり上げる場所が、学校。そういった積み重ねが、世に出て、生きる力になる。
西郡学習道場代表 西郡文啓