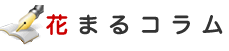『6才の夏、おじいちゃんと虹の思い出』2024年7・8月
その記憶は、実家の玄関先から始まる。
私は祖父に連れられ、手をつないで家を出る。そんな祖父と私の後ろ姿を、母が送り出す。ふりむくと母が手を振っていた。いつもの笑顔のなかにも、その表情がどこか不安そうだったのを覚えている。
初めて、祖父とふたりだけでお出かけしたのだ。当時、私は小学一年生。祖父にとっては初孫だったということもあり、かわいがられていたことは容易に想像ができる。
父母の結婚に反対だった祖父は、私の誕生により母と父を許すことにしたそうだ。子どもは存在するだけで、周囲に影響を与えている。何もないところから、子どもは存在することで、幸せを生産しているのだ。
行き先は母の実家。どんな成り行きでそういう習わしになったのかはわからない。夏休みになると私ひとりで、山のなかの祖父母の家に行く。はじめてひとりで、お泊まりをしにいくのだ。母が不安そうな表情になるのも、無理のない話である。
いくつかの山を越え、小さな坂道を上った先にある祖父母宅には、大きなさくらんぼの木があって、たくさんのカタツムリや、虫の幼虫、見慣れないほどの大きなアリの行列を眺めることができる。虫好きな私には大好きな場所だった。
さて、私にとっては大好きな、よく孫に会いに遊びに来てくれる「おじいちゃん」。それなのに、たとえ大好きなおじいちゃんにも、当時の私は甘えたりできない子どもだった。
「かわいがってくれる祖母、叔母や父に対しても、遠慮したり気遣ったり、言いたいことを言えない」……幼稚園の連絡帳には、登園をいやがる私の状況とともに、母の字でそう記されていた。
超がつく引っ込み思案。そんな6歳の私と祖父とのふたりきりの車内。黙ったまま前を見て座る私。数十分のドライブ中、どうやって過ごしていたのか、その場面は霞がかかっている。
記憶に色が戻るのは、山に向かって走っていく道々、目の前の空に、突如、虹が見えてから。私の緊張が一瞬解けたすきを狙ってか、祖父は私に問いかける。「虹の色は言えるか?」と。声を出せずにいる私に「最初は赤から始まって、橙、黄色、黄緑、緑、青、その次は何かわかるか……」と話し続けてくれる。
ホッとしていると祖父の質問は続く。「ほんなら英語で言えるかなぁ、赤はレッドやなぁ、橙は知っているか……?」描くことが大好きな私を知っている祖父にとって、きっとこの話題なら、と話し続けてくれたのだろう。
初めての、祖父とのドライブ。祖父とふたりだけで外出したのは人生でほんのわずかしかないが、その記念すべき第一回が、虹の思い出なのだ。美しい色彩が重なるように、淡い色の抽象画みたいに、あのときの記憶が私の脳裏に明るい光を残している。
孫との初ドライブをする祖父も、見送る母も、そして私自身も、心細かったに違いない。その不安をいっとき忘れさせてくれたのが、山の合間に見えたはかない虹だった。
私が8歳の春に亡くなった祖父との会話(私は話していないけれど)は、覚えているなかでこれが一番長いものとなった。いまでも虹を見るたびに、私の心には、あの日祖父とのドライブで一緒に見た、流れる山々と虹の色の思い出が、よみがえるのである。
井岡 由実(Rin)