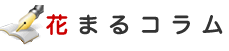『自分らしさはどうやったら生まれるのか』2025年2月
「自分らしさ」を表現してほしい、と願わない親はいません。それゆえに「人と違う、唯一のオリジナリティ」という幻想を、作品に期待してしまう。「こうあってほしい」という願いは、ときに子どもたちをがんじがらめにします。
創作を始める前に必ず確認する「きはん」の時間。私が「まねっこするのも大歓迎」と伝えると、ホッとした顔をする子どもたちが少なからずいます。
ある一年生の男の子。運動や音楽が大好きで活発な性格ながら、慎重で繊細な一面も持ち合わせています。負けず嫌いで失敗することに抵抗がある彼は、図工の時間、真っ白な画用紙を前にして泣いていました。
家での工作や遊びのときも、「どうしたらいいの?」とお母さんにまず聞きます。「自由に、すきなように描いていいんだよ」と伝えても「何したらいいかわからないもん」「上手にできないもん」と悩んで、手が止まってしまうのです。
手が止まる原因はさまざまです。とにかく“失敗”したくない気持ちが先立っている場合、そもそも頭のなかに具体的なイメージが浮かんでいない場合、またはイメージはあってもそれをどう表現すればいいのかがわからない場合など。
どんなのものをつくりたいのか、本やネットで一緒にお手本を探してみたり、「ママはこんなふうにやってみようかな~」と描いてみたり……。そんなことを繰り返しやっているうちに、 いったんやり方がわかると、それをトレースしながら少しずつ自分のオリジナリティを出した作品をつくれるようになる、ということに気づいたそうです。
インプットすること、真似ること、これが「自由な創作」をするためには必要だということ。頭ではわかっていたことだけれど……とお母さんは気づかれました。
「学ぶ」は「まねぶ」が語源ですし、「型」があるから「型破り」ができます。「すべての創造は模倣からはじまる」という言葉のように、私たちは、ありとあらゆる情報を吸収して、日々学んでいく生き物なのです。
「先生が提案するものや、仲間が思いついたおもしろそうなアイデアを、それやってみたい! と思ったなら、その“やってみたい”気持ちに正直でいて。いつも自分の心が何に動いたのかを、大事にしてください」
「絶対に同じものはできないし、それぞれが唯一で世界一の作品になります。自分らしさはどうやったって消えないし、それは何かによって奪われるものではないんだよ。あなたらしさを信頼して」
教室で子どもたちに「真似をしてもよい」と言い切ることの意味。
それは、あなた自身のフィルターを通した世界観というものは、絶対に失われることのないものなのだ、と知ってほしいからです。
他人の評価に沿って正解を目指して生きているうちに、見失ってしまうあなたらしさ。大人だってそうです。目の前のやるべきことを、ただ真摯に取り組むだけで、あなたらしさは勝手に滲み出てきます。
自分の物語をつくるために生まれてきた私たちは、すでに生きているだけで、その人らしさを奪われることはないのです。
子どもたちがたくさんの経験をして、もともと持っていた種から花を、豊かに実らせることができますように。そんなイメージで、子どもたちの前に立ち続けるのです。
井岡 由実(Rin)